ブランド戦略の事例を知る
瑞穂酒造・株式会社OneSpirit×沖縄黒糖 ~沖縄が誇る素材が切り開いた世界へ通ずる道~
2025/03/06
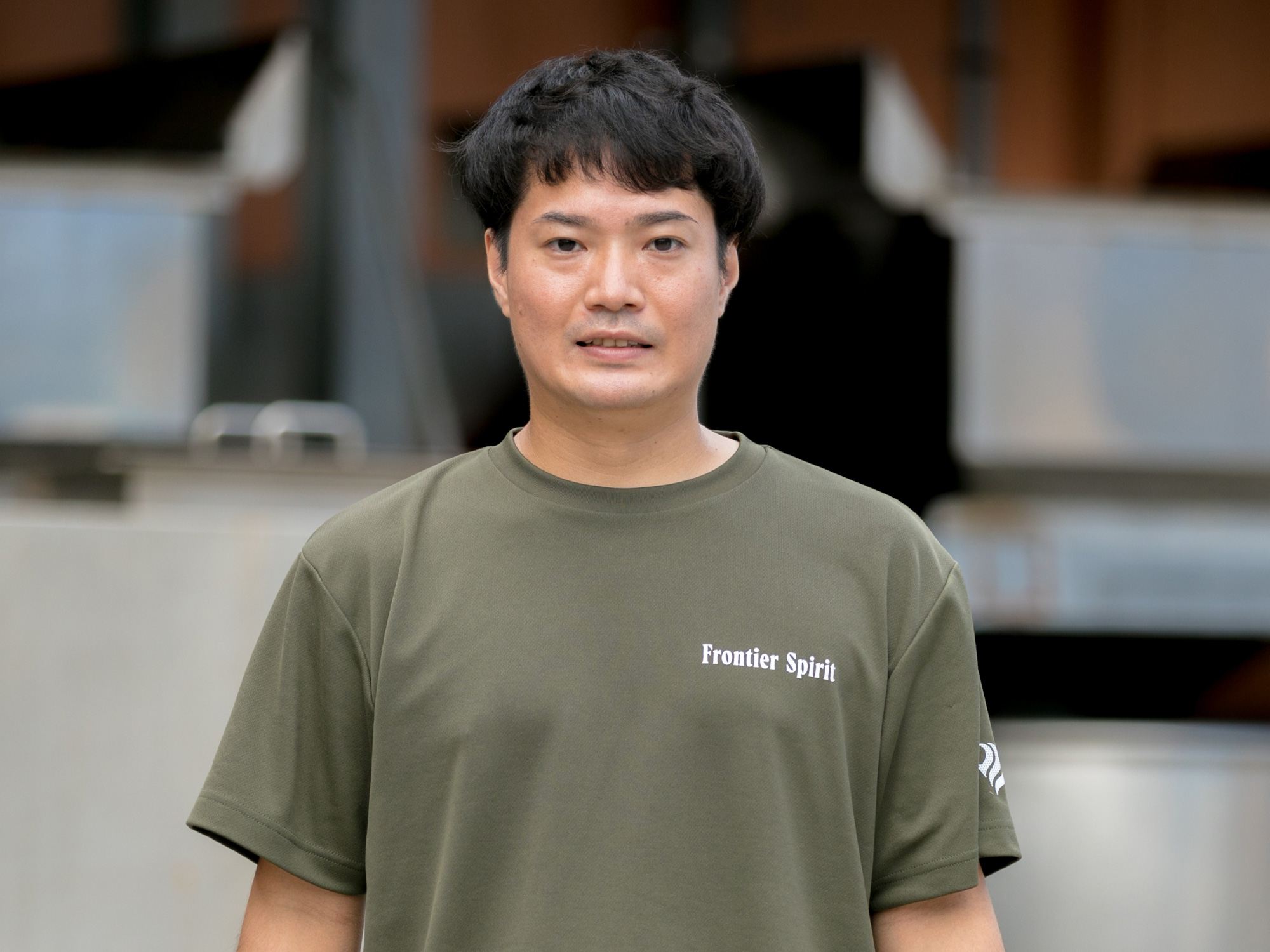
瑞穂酒造株式会社/株式会社OneSpirit
仲里 彬 様
沖縄伝統の酒・泡盛を製造する瑞穂酒造、その技術とものづくりの精神を継承しつつ新たなチャレンジにまい進する株式会社OneSpiritと、沖縄が誇る素材・黒糖がコラボレーションし、個性豊かなラムを開発。
黒糖と向き合い次世代へとつなぐプロジェクトはどのように発足し、何をもたらしたのか。
今回は、177年の歴史を持つ瑞穂酒造で商品開発を手掛け、また株式会社OneSpiritの代表取締役を務める仲里彬様にお話を伺いました。
産業間連携のPOINT
| 連携している産業 | 泡盛製造業 X 黒糖 X 食 |
| きっかけ | コロナ禍を契機に、瑞穂酒造が200年企業となるために、企業理念を見直したことがきっかけ。沖縄の課題に対し自分たちがものづくりでできることを検討した結果、当時、供給過多となっていた黒糖に着目した。 |
| 大変だったこと | 特になし |
| メリット | 黒糖という沖縄の素材でラム酒というグローバルスタンダードなお酒ができ、世界とつながることができたこと。 |
| 効果 | 泡盛製造だけではリーチが難しかったお客様や世界に向け、販路が拡大。 |
瑞穂酒造、また株式会社OneSpiritについて教えてください。

(仲里)1848年に酒造りを始めた瑞穂酒造は、今年で177年目を迎えます。琉球王朝時代には泡盛は貴重な酒として管理され、首里三箇と呼ばれる三つの地域でのみ造られていましたが、瑞穂酒造はその一つ鳥堀にて創業した、沖縄で2番目に古い蔵です。伝統的な古酒製造を守り続けることはもちろん、その時代その時代のニーズに応えるべく先人たちは様々なことにチャレンジしながら、歴史を紡いできました。
株式会社OneSpiritは、そうやって先人たちが培ってきた技術とチャレンジ精神を受け継ぎ派生した企業です。そうやって先人たちが培ってきた技術とチャレンジ精神を受け継ぎ、近年当社では、伝統的な技術をベースに、時にはイノベーティブな技術にチャレンジし、沖縄の地域素材と様々な可能性を掛け合わせてものづくりを行っています。「黒糖を原料としたラム酒づくり」も、そのチャレンジの一環として取り組んだものになります。
また、OneSpiritはそれらアクションについて、世界に遅れぬよう、よりスピーディかつ大胆に、外部のコラボレーション等も踏まえた、酒類の企画・販売を手掛けるグループ企業となります。
具体的には、どのような商品を提供しているのでしょうか。

(仲里)沖縄の離島8島でつくられる黒糖を原材料としたラム酒を、Single Island Series(シングルアイランドシリーズ)として製造・販売しています。8島とは黒糖の製糖工場がある、粟国島、伊江島、伊平屋島、西表島、小浜島、多良間島、波照間島、与那国島のことです。
また、8島の黒糖の個性を豊かに表現したラムの原酒をブレンドして仕上げた「THE OKINAWA ISLANDS RUM」も展開しています。
どのような背景で、黒糖とのコラボレーションに至ったのでしょうか。

(仲里)大きなきっかけは、コロナ禍に離職者が急増したことでした。この状況を受け、200年企業として維持・発展していくためには企業としてどうあるべきか、全社活動として瑞穂酒造の進むべき道、企業理念の見直しをはかりました。様々なワークショップに参加する中で出会ったのが、アリストテレスの哲学です。「世の中の課題」と「あなたができること」がまじわることこそが「あなたが進むべき道」だというフィロソフィーは、企業活動でも同じこと。今、私たちがやるべきことは、世の中、特に日本と沖縄の課題にしっかりと目を向けること。そして、自分たちができるものづくりでアクションを起こしていくことだと考え、沖縄の課題を探すワークショップを全社員で行いました。100個200個と課題が出る中で着目したのは、さとうきびが抱える様々な課題。その中でも特に、黒糖が供給過多で余っていたこと。これを活用した取り組みができないか検討を進めました。
また一方で、ラムの需要がグローバルで見ると拡大していくというデータに目が留まりました。そこで、これまでのラム酒づくりとは一線を画すような製法で、世界に通用するラム酒を展開していこうと、産官学はもちろんバーテンダーなど各方面の人と力を合わせて「ONERUM」というプロジェクトを発足。そこから黒糖とのコラボレーションがスタートしました。
黒糖からのラム酒づくりでは、開発は順風満帆に進んだのでしょうか。

(仲里)時間を要したのは、離島8島それぞれの島の風土や生産方法の違いから生まれる黒糖の個性を引き出し、表現することです。黒糖の味が島によって異なっているからといって、すべてを同じような製法でつくったのでは、その風味の差は思ったほどには出ません。まずはすべての島へ出向き、島の方々にさとうきびや黒糖の特徴、そして島そのものの魅力をご指南いただき、各島の特徴を理解しイメージを固めてコンセプト化したものを、どのような製法でどう表現していくか……。昼夜を問わずの研究開発と、幾度とない試作を重ねた結果、8島の黒糖の個性を引き出すための技術を開発するに至りました。
研究開発は時間がかかるものですが、このプロジェクトは2023年の沖縄に黒糖が伝わって400年となる節目の年にリリースすることが決定していました。2年弱の準備期間で、まったく異なるフレーバーのラム酒を8種類つくるということは、時間的な制約もあってとてもチャレンジングな取り組みでした。
他にも産業間で連携した取り組みはありますか。

(仲里)「ONERUM」プロジェクトを立ち上げるにあたり、バーテンダーの方とはテイスティングなど開発段階から連携しています。また、できたラムをどういうカクテルでアプローチしていくかの開発についても協力を得ました。開発段階から一緒にチームに入っていただくことで、畑からラム酒を楽しむ場面までを一連して開発しているのはこのプロジェクトの特徴のひとつです。
また、世界一のバーテンダーである後閑信吾さん率いるSG Groupとの連携もあります。コラボレーションのきっかけは、国内外でバーを展開するSG Groupが沖縄に店舗をオープンしたことです。1杯のカクテルをつくるために、沖縄県下のレストランや畑を訪問していた後閑さんは、当社にもご来社いただき、その時に目に留まったのが、泡盛と黒糖でした。世界的にはまったく認知されてはいないけれど、ポテンシャルがある黒糖や泡盛を使って沖縄が抱える課題を解決するアクションを起こそうと、プロジェクトが誕生し、泡盛と黒糖、黒糖ラムを原料としたリキュール「KOKUTO DE LEQUIO(コクトウ デ レキオ)」を開発しました。黒糖の可能性を追求したこの商品は、SG Groupが持つ海外へのコネクションにより世界に発信されました。私たちの企業単独では決してリーチすることができかなったところに、もっと黒糖を届けていきたいと思っています。

産業間連携によるメリットについて教えてください。
(仲里)泡盛は、沖縄や日本では歴史のあるお酒ではありますが、世界的認知はまだまだ低いローカルスピリッツです。沖縄の素材である黒糖を使ってグローバルスタンダードであるラム酒をつくったことで、世界中のお客様に知っていただき、販路を拡大できました。泡盛だけをつくっているのでは届けることができなった層にリーチできたのは、大きなメリットです。
また、黒糖ラムをきっかけに、海外の方々にも「日本の沖縄には泡盛というローカルスピリッツがある」ということを知っていただくことが多分にありました。沖縄にサトウキビと黒糖がこんなに豊富にあるということも知っていただけたのは、ひとつ成果だと思っています。中には「泡盛の原料はなぜ黒糖じゃないの?」とお問い合わせもあるほどです。地元のものを使ったお酒づくりの必要性・重要性を、あらためて実感しました。
産業間連携により消費者にどのようなムーブが起こるとうれしいと思いますか。
(仲里)ウイスキー好きが蒸留所を聖地巡礼して回るように、8島に足を運んでくれる方が増えたらいいなと思っています。今でも県内外のバーテンダーの方がこの黒糖ラムを持ってそれぞれの島に訪れて写真を送ってくださることがあります。ラムをきっかけに島を知っていただいて、実際に足を運び現地での体験を楽しんでもらうというのは、このプロジェクトをやって良かったなと思う一番うれしいことです。
今後、予定しているコラボレーションについてお聞かせください。
(仲里)2024年にモンゴル800の上江洌清作さんとコラボレーションして、黒糖ラムをベースに、沖縄県産のレモングラスなどを使用したクラフトジンを開発しました。清作さんの音楽からインスピレーションを受けて商品をつくるというプロジェクトで、歌詞をすべて文字に起こして「この歌詞の意味であれば、どのような香りが連想されるな」「それを実現するためには、どのような素材が使えるかな」と、全工程を清作さんと取り組み、最終的な味の決定は清作さんにしていただきました。
このプロジェクトは、毎年11月に開催される音楽フェス「What a Wonderful World!!」に向けて、1年1曲ずつ取り組みを続けていく予定です。将来的には「お酒のアルバムをつくろう!」という目標を立てています。音楽をきっかけに、お酒はもちろん、その先にある黒糖や沖縄地域の素材の魅力を清作さんを通じて発信し、あらたな層に届けていきたいと思います。
